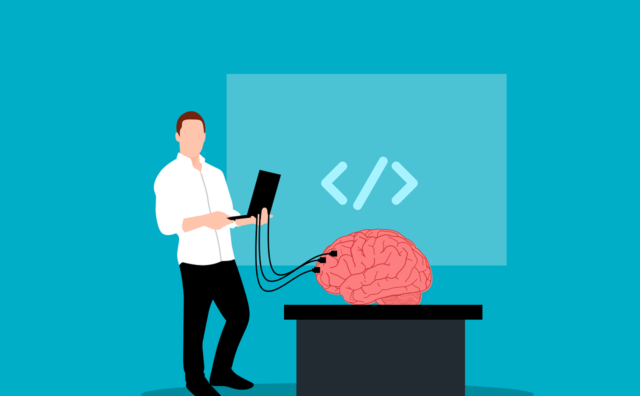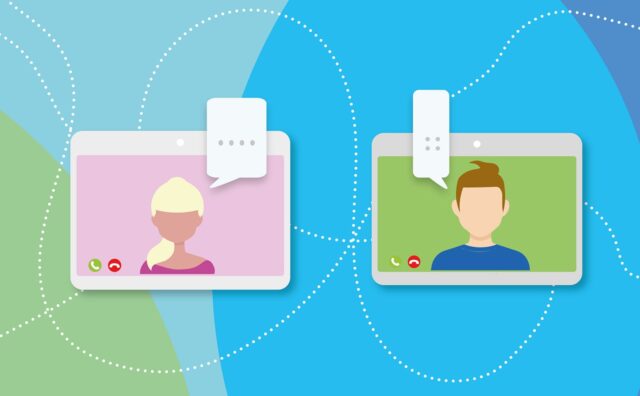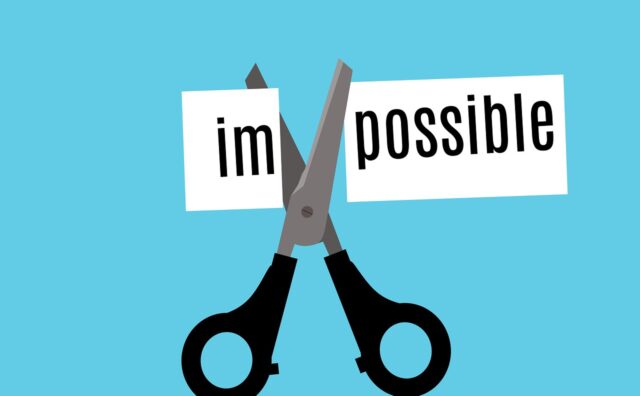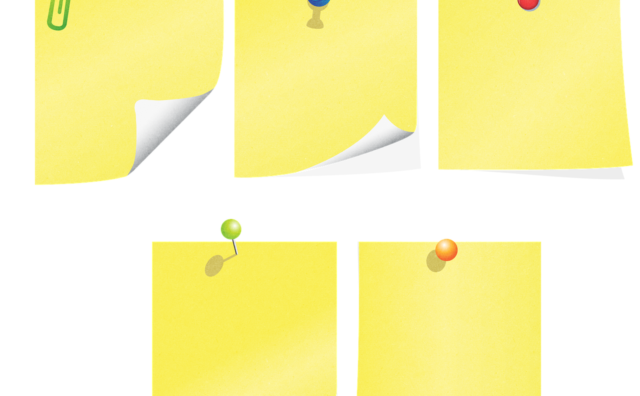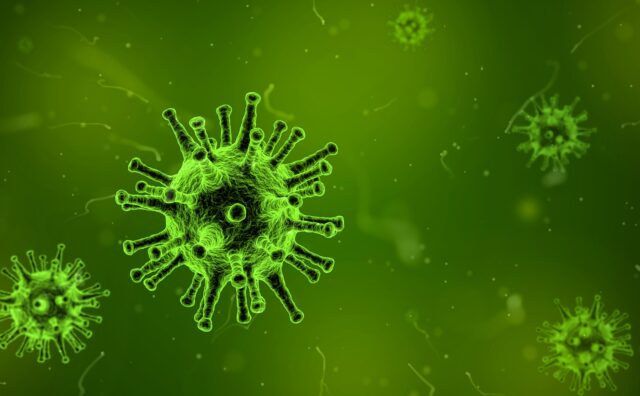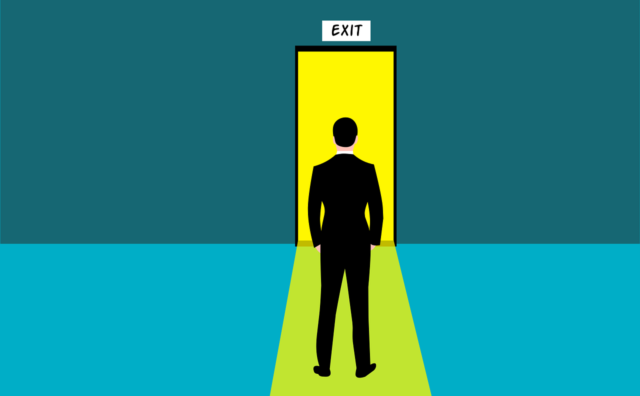学校内での人間関係は、学校生活という期間が、
幼稚園から高校生までとした場合でも
せいぜい15年間にすぎません。
人生80年以上と言われる時代です。
15年という期間が長いと思うか短かいと感じるかは個人差がありますが、
学校生活は、家族という小さな集団から離れて
初めて体験する
社会に出る前の大切な期間です。

学校内と現実社会の人間関係を比べて、
学校内での過ごし方、取り組み方を書き記してみました。
同級生同士の人間関係
普通の学校では、クラス替えは一年に一度です。
気の合う仲間と一緒になれたと喜んでいる人と、
嫌でも一年間は仕方ない、と思って過ごす人がいると思います。
社会でのクラス替えと同等なものは、
大きな会社では部所の移動、
小さな職場では部所の移動は不可能ですから転職ということになります。
学校では、クラス替え以上のものは転校ということになります。
ただ移動先(転校先)が必ずしも気に入ったものとは保証されませんし、
そこまで考えなければいけない場合、
いじめやパワハラなどの大きな問題の解決が必要になります。
そもそもクラス分けはどのようにして決まるものかというと、
一言でいうと、クラスごとのバランスをできるだけ均等にするということです。
具体的には、小学生低学年の場合は月齢差まで考慮されたり、
体力差、成績、リーダー性、積極性のある無しなど、
偏りが少なくなるように分けることだと言われます。
(小学生、中学生。高校生によって違ってきます。双子はひとクラスでない限り必ず別々のクラスにされるそうです)
このようにして決められたクラスが決して完璧にそうなっているかというと、
それは無理というもので、クラスの数が多ければ多いほど難しいものです。
しかし決まったからには、そのクラスで少なくても一年間は過ごしていくことになります。
決めつけてはいけないのでしょうが、人は孤立するのが不安なものです。
特に学生時代!思春期の頃は誰かと一緒に居ないと、仲間外れにされたように感じるものです。
多くの場合、男女とも少人数のグループが出来上がり、
グループごとに行動することが多くなります。
従って、このグループに入れなかった人は孤立するということになります。
職場でも同じように派閥という形でグループができ、
学校と違う大きな点は、利害関係が大きいというところです。
単純にグループ分けされた単なる仲間や遊び相手だけでなく、
出世が絡んできたり、損得で成立するグループも出来上がります。
もちろん学校と同じように一緒に旅行に行ったり、
食事に行ったりする、損得抜きで付き合えるグループもあります。
学校で孤立しそうになった時、やってほしいことは
自分の得意なこと、自分の好きなことを見つけてそれに没頭することです。
そして、それを人がうらやむほど、極めること。
それが学校とは関係ないものでも構いません。
例えば
ゲーム・歌・ダンス・楽器・パソコン・絵・アニメ・何かを収集する...etc
学校以外で仲間や知り合いができたら、
学校の中の小さなことは、大きな問題にならなくなります
。
もちろん、簡単なことではありませんが、
要は、学校とは違う世界を自分で見つけ、
学校という、小さな世界に縛られないようにしていくことです。
そういうことができた時、クラスメートからは、
あなたが自信に満ちあふれて見えるようになるものです。
それでも、それすらを妬んで陰険なことをしてくる人もいるかもしれませんが、
世間ではそういう人は通用しなくなります。
人が良くなっていくこと、成長していくことを素直に喜べないで、
邪魔をする!妬む!こんなクズ人間とは関わらないようにしましょう。
そして、もしあなたが、そちら側の人なら考え方を改めましょう!
小学校ではクラブ活動として4年生から、中学校からは部活として、
運動部か文化部に分かれて、希望者が参加するというのが一般的です。
年齢の違う者同士が指導者の協力を得て、自分たちのやりたいことを自主的に行動したり、
作り上げたり、集団の中の一員として活動することが部活の目的です。
運動部なら体力やそのスポーツに特化した技術の向上、
文化部なら専門知識や技能を習得するということです。
特に運動部ではそのスポーツのルールを覚えたり、技術を向上させたり、
文化部なら社会人を超える技能を学生時代に習得することも不可能ではありません。
また部員同士のコミュニケーションによって、
社会に出る前のコミュニケーション能力を身につけることもできます。
仲間と過ごすことで、気持ちがリフレッシュしたり、ストレス発散にもなります。
クラスメートに馴染めなくても、部活で別のクラスの人とは気が合うということもあります。
そうは言っても、良いことばかりではありません。
例えば、運動部などでは、同級生同士でも運動能力の差によって、
レギュラー選手になれたり、ずっと控え選手でいたりもします。
またあってはならないことですが、人数の多い人気の部活などでは少人数の派閥もできあがり、
理不尽な思いをする人も出てきます。
運動部には少なからず、正当でないしごきなどという制裁もあります。
このような問題は、同級生同士で解決できることではないので、
泣き寝入りしたり、闇に葬るのではなく、
正当な判断ができる人物に相談・依頼して必ず解決していきましょう。
このようなことは、当然社会にはもっと理不尽なことが加わり存在します。
先輩(上級生)・後輩(下級生)との人間関係
学生の時、中学からは、先輩(上級生)というのは最上級生でも2歳しか違わないのに、
すごく年上に思えるものです。
学校では一学年違うだけで、大きな差があるように感じられますが、
社会では歳の差より経験と実力が大切になってきます。
ひと昔前のような年功序列式【勤続年数や年齢で職場での賃金や地位が上がっていくということ】の企業は今後おそらく存在すら危ぶまれるはずです。
上級生と関わるのは部活での場合が一番多く、妙に先輩風ふかせたい人がいたり、
温かく迎えてくれる人がいたりで、そこは世間も同じです。
謙虚に普通に接していれば何も問題はありませんが、いろんな人がいるのも確かです。
学生時代に尊敬できたり、あこがれる存在の先輩に出会えたら幸運です。
反対にパワハラ的な扱いをしてくる先輩もいるでしょうが、
そんな人も社会に出たらただの人です!
自分が選んで入部した部活なら、他人のことより、部活そのものを楽しんだり、
知識や技能を磨くほうに力を注いでください。
後輩を大切にできる人であってください。
自分が先輩にいじめられたから、パワハラを受けたからと、
今度は自分も後輩にそうしてやるんだという未熟な考えをしないでください。
後輩との接し方は、自分が先輩にされて嫌だったことをしない!
自分がされてうれしかったことを思い出して接してください。
ただ見栄を張ったり、自分を大きく見せようとカッコつけたりすると疲れるので、
自然体で臨んでください。
この関係は社会に出ても同じことが言えます。
後輩と協力しあう、という関係は、学校でも社会でも、あなた発信でできることです。
先生との人間関係
学生時代に関わる先生と言えば、
部活をやっている人は、部活顧問の先生。
何か特別なことを学びたい人は、教科担当の先生。
あとは担任の先生です。
ただ先生とフレンドリーに話せる人は少ないのではないでしょうか。
先生というのは敷居が高いというか、なんとなく敬遠しがちな存在です。
金八先生のような先生は稀です。
私が学生の時は、先生とフレンドリーには話せませんでした。
今となっては、もっと相談したり、教えてもらっておけばよかったとつくづく思います。
だから皆さんにはそうして欲しいと思います。
先生も同じ人間です。
もしかしたら、皆さんからの問いかけを待っているのかもしれません。
社会では何か習い事でもしない限り、直接の先生というのは存在しませんが、
仕事や世間の道理を教えてもらうという意味で、
職場の先輩や、上司が先生と言えるかもしれません。